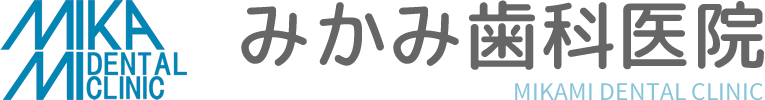小児診療
PEDIATRIC DENTISTRY子供の虫歯予防

小児の虫歯予防の原点は、母親にあると言ってもよいでしょう。生後10ヶ月~31ヶ月の間に、虫歯菌であるミュータンス菌が母から小児へと感染していきます。その時の条件は、母親の口腔内にミュータンス菌が大量にいる場合、又、小児がショ糖(砂糖)をたくさん摂取している場合に、効率良く感染していきます。
子供の場合、歯ブラシの習慣はもちろん大切ですが、むしろ糖分のとり方や、食生活の方が虫歯予防にとっては重要であると言えます。
当院では、おやつの与え方、歯ブラシの方法、歯並びのチェックやよりよい習慣がつけられるようにアドバイスをしています。
シーラント
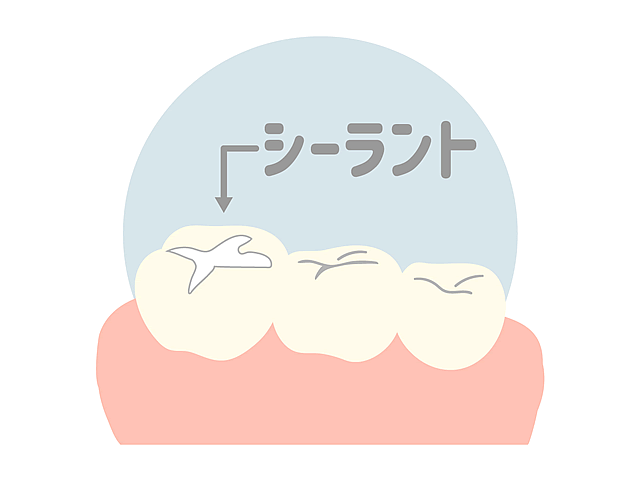
当虫歯になりやすい奥歯の溝を樹脂(虫歯を削ったとき詰めるものと同類)で埋めてしまう予防法です。歯を削らないため、はがれることもありますが、特に虫歯になりやすい生えて間もない奥歯の永久歯に有効です。しかし、歯と歯の間の虫歯予防にはなりません。シーラントをしたからといって、ブラッシングをきちんとしないのは逆効果になってしまいます。
フッ素塗布
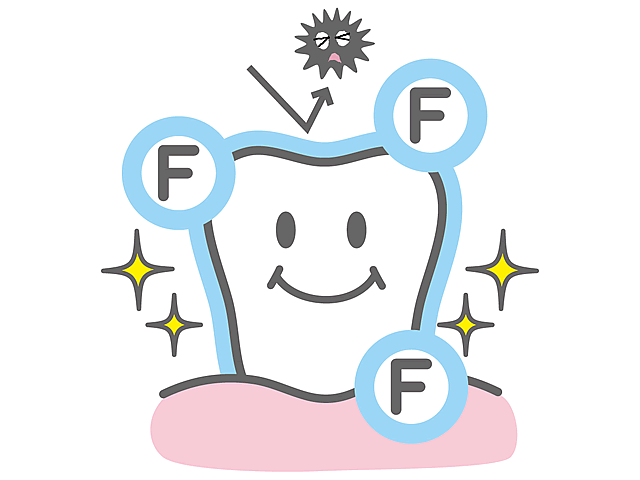
「フッ素」は自然界にもいたるところにある物質で、自然元素のひとつです。海水の中にも含まれ、毎日の食事を通して私たちのカラダに摂取されている必須栄養素のひとつです。歯質を強化する効力が最も高いことから、世界各国で虫歯予防に利用されています。けっして車のワックスのように歯の表面をコーティングするようなものではないので、定期的に塗布の必要があります。乳歯や生えたばかりの永久歯に非常に効果的です。
塗布後30分はうがいもできませんが、最近はリンゴ味などのフッ素剤があり、医療機関で行うものと、家庭で行うものがあります。栄養素のひとつでも、多量に摂取すると危険です。多量に誤飲しないように家庭では濃度の低いフッ素剤を使用するようにしましょう。
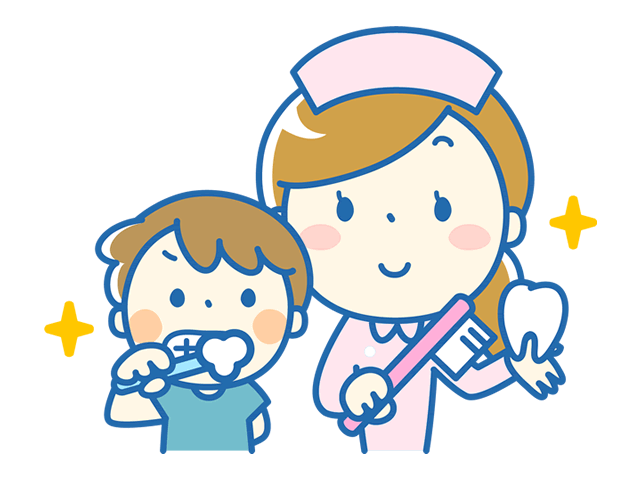
医療機関で塗布
高濃度のフッ素溶液を歯科医師の管理下で年3~4回(3~4ヵ月ごとに)行う方法です。小さなお子さんでも塗布することが可能です。塗布後、30分間はうがいができません。以前のフッ素溶液(ジェル)は後味の悪い物しかありませんでしたが当院ではリンゴ味のフッ素ジェルを使用しています。予防なので保険適応外です。
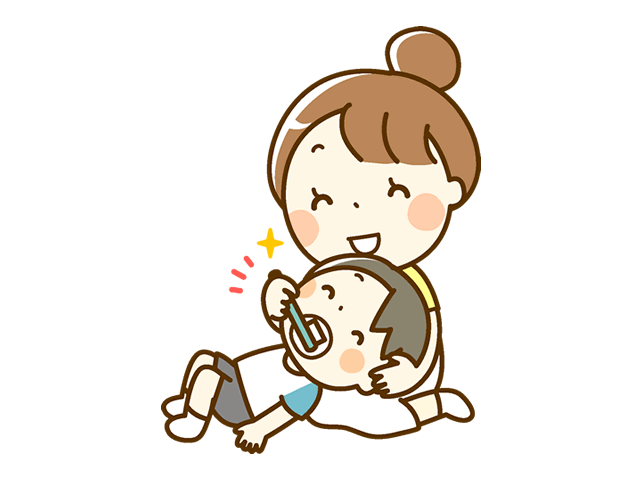
家庭で塗布
虫歯予防効果は家庭で低濃度のフッ素溶液を毎日利用することが効果が高いと考えています。当院では、家庭で使用するフッ素ペーストの使用方法をご希望の方に指導しております。
乳歯の抜歯
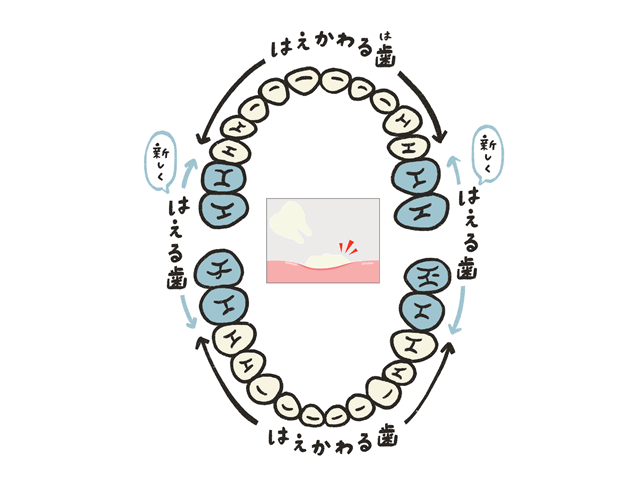
乳歯は生え代わりの時期が来るとぐらぐらしてきて抜けてしまいます。しかし、乳歯がひどい虫歯の場合、あるいは何らかの理由でうまく抜けなかった場合には医療機関で抜く必要があります。
あごの骨の中で育っている永久歯の生えようとする方向が悪い場合には自然には抜けない場合が多いです。その場合は時期を見て乳歯を抜く必要があります。そのままにしておくと永久歯の歯並びが悪くなったり、かみ合わせが悪くなります。
自然に抜けない場合があることを知って、抜け変えの時期は口の中に注意してあげるとともに、この時期には定期的に医師にみてもらいましょう。
子供の
歯みがきポイント

乳歯や生えたばかりの永久歯を虫歯から守るためには「歯磨き」が非常に重要です。また、大人になってから歯磨き習慣をあらためるのはたいへんです。夜寝る前の歯磨きは当たり前、奥歯の裏側もきちんと意識して磨くのは当たり前、食後すぐ歯磨きをしないと気持ち悪い・・・という習慣をつけてしまえば、その人の一生はずいぶん違うものとなるでしょう。
年齢に合った歯磨き(親が磨いてあげる→手伝ってあげる)で、歯の隅々まで磨く習慣をつけてあげましょう。また、歯磨き剤を使うと実際に磨けているかどうかもわからなくなりますので、水だけを付けて歯磨き剤は使わないようにしてください。当院ではその年齢に合った歯磨き指導を行っていますのでご相談ください。
嚙み合わせ治療

噛み合わせの異常があると噛む機能がうまく働かないだけでなく、体や顔のゆがみ、病気の原因になることもあります。小学生までの間に適切な治療を受けると、大掛かりな矯正治療をうけずにすむ場合もあります。
指しゃぶりなどの癖を取り除くことで、予想される不具合が起きないようにします。永久歯に生え変わる成長期でアゴの骨がよく発達する時期で すので、大切な永久歯を抜かず、本格的な矯正治療を受けずに歯並びを整えることも可能です。
食育で虫歯予防

乳歯や生えたばかりの永久歯は虫歯になりやすいです。小児は甘いものを口にする機会が多く、しかも間食も多くなりがちです。甘いものは癖になります。甘いものの食べすぎは食事時の食欲を減退させ、糖分の消化には、多くのビタミンとカルシウムが必要となり、栄養のバランスがくずれてしまいます。食のバランスをよく考えてる事が大切です。
少なくとも3歳未満の小児には、キャンディー類、チョコレート類はできるだけ食べさせないようにしましょう。食べたことがないと欲しがりません。低年齢児の味覚はまだ未発達です。この時期に甘みの強いものを与えると味覚の発達が妨げられ、野菜などの味がよくわからなくなり、好き嫌いが多いこどもになってしまいます。食生活が親のコントロール下にある時期に正しい食事をする事がもっとも大切だと思われます。
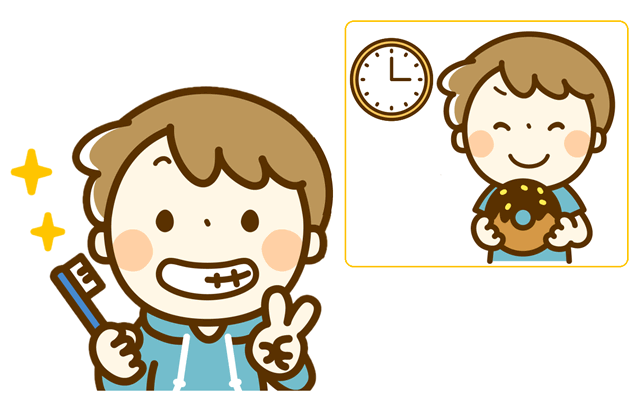
おやつの与え方
砂糖だけでなく多くの炭水化物は細菌によって代謝され酸が作られ、歯を溶かします。断乳の遅れは虫歯が増える原因になるといわれています。口の中に糖分のある時間を短くすることが大切です。食事やおやつ以外にジュースを飲むことはしないで、お茶などにし、3歳児以上は「~を食べたらダメ」ではなく、決まったおやつの時間に食べるように、飲食の回数を少なくすることが大事なのです。ダラダラ食いをやめることは非常に効果があります。
- 決まった時間に食べましょう!
- 1回の食べる量を決めて食べましょう!
- 栄養のバランスを考えましょう!
- チョコレートやキャンディなど甘さがいつまでも残るおやつは注意しましょう!
- あごを使って噛みごたえのあるおやつを食べましょう!
- おやつの後も歯磨きをしましょう!